動画制作はどんな流れで作るのか?
知っているようで、聞かれるとうまく答えられないことってありますよね?
全体の動画制作の流れを知っていれば、予算相場や外注先の得意分野の把握など、全体図が掴みやすくなって、失敗が少なくなります。
というわけで、今回の記事では『動画制作を始めたい』または『発注担当者の方』に向けて、動画制作の流れとともに、動画制作を始める上で最低限の知識をご紹介する記事です。内容は
●動画制作の全体の流れ
●動画制作に必要なソフトや機材
●やっぱり外注!?と思ったあなたへ【動画制作会社を選ぶポイント】
です。
今回の記事では、動画初心者の発注担当者さん向けに、読むだけでわかる『動画制作』の基礎をお伝えします。
動画制作4つのStepは?|全体の流れを解説
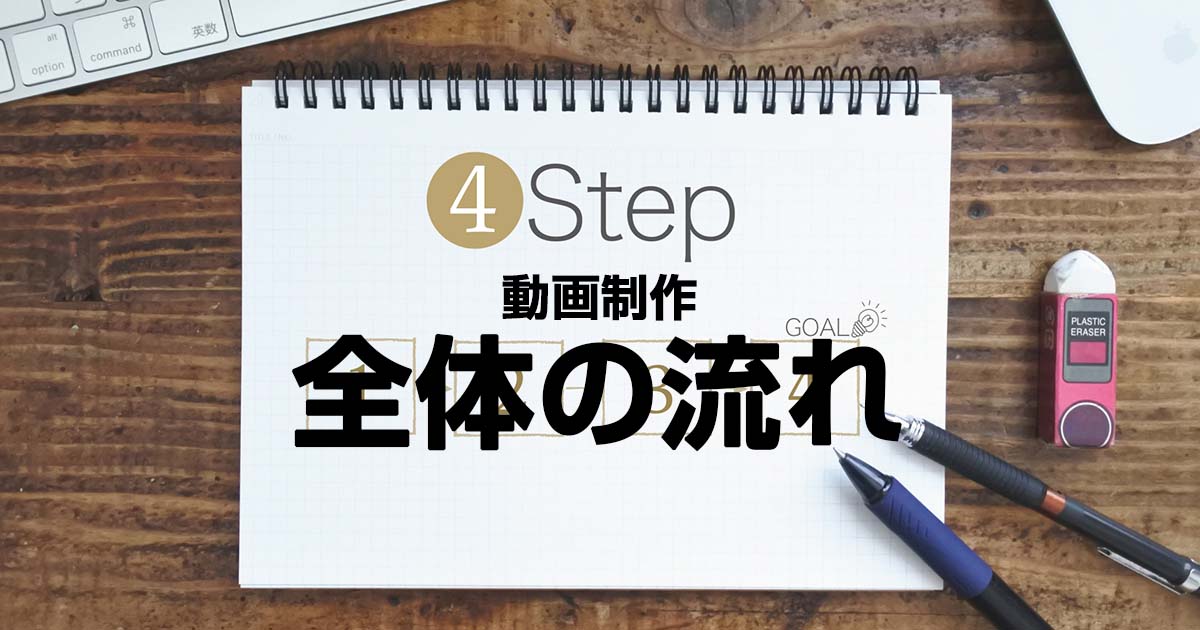
まずは、動画制作って、どんな流れで作っているのか?についておさらいしましょう。
動画制作には、4つのステップがあります。
動画制作の手順は「企画・構成」、「撮影」、「編集」、「公開」の4ステップです。
①企画・構成
②撮影
③編集
④公開
各項目について詳しく見ていきましょう。
①企画・構成で動画制作の方向性を決める
動画制作と言っても、目的はさまざまです。
企画・構成は、動画制作の方向性を決める上で重要な作業です。
動画の仕上がりを左右しますので、きちんとポイントを絞りましょう。決める内容は下記の3つです。
(1)テーマを決めよう!何を伝えたい動画制作か?
(2)ターゲットは誰か?誰に動画を見て欲しいか?
(3)TV?YouTube?どこに動画を公開するか?
動画制作の企画・構成では、これらのポイントを明確にするのが必要となります。
②撮影のポイントは?
動画制作の撮影で気を付けるポイントは以下の通りです。
●基本的にカメラは固定
●音声にも配慮
●照明は必須
●カメラアングルと構図を覚えてワンランク上を目指そう
そのほか、撮影日や出演者、内容はもちろん、なにをどんなスケジュールで、どんな機材を揃えておくのか?など、細かいことまで準備しておくことが大切です。

③動画編集の5つの手順
撮影した映像素材を繋ぎ合わせ、一つの動画に仕上げるのが編集作業です。たとえば30分の動画を作るための撮影なら、撮影素材はそれ以上です。
編集は、不要な部分をカットするところから始まり、繋ぎや、テロップ、効果音、ナレーションなどの演出を施していきます。そのため、動画制作の中でも最も時間がかかりやすく、地道で細かい作業が続きます。
また、同じ映像素材を使っても、編集次第で全くの別物になります。そのため、企画・構成で完成イメージを明確にしておくのが重要なのです。
(1)撮影素材の読み込み
(2)不要な部分をカットする
(3)テロップを入れる
(4)BGM&効果音を入れる
(5)動画を書き出す
④公開して動画制作が完了
動画が完成したら、あらかじめ決めておいた媒体に公開して動画制作が完了です。
インターネット上に動画を公開する場合、現在はYouTubeにアップロードするのが主流となっています。
企業または個人でYouTubeチャンネルを開設し、制作した動画を公開して下さい。動画のURLとSNSを連携させると、より多くの視聴者にアピールできます。
動画制作の撮影時に必要な機材は?


動画制作の編集に必要なハードとソフト
動画制作の編集には、パソコンを使います。そして動画の編集には、無料から有料まで、たくさんのソフトがあります。
ここでは、動画編集をする上で必要なスペックと、オススメの動画編集ソフトをご紹介します。
●動画編集に使うパソコンは?
●動画制作にオススメの編集ソフトは?
動画編集に使うパソコンは?
動画編集をするパソコンは、ある程度のスペックが必要です。
・CPU:intel Core i5、Core i7、Core i9
・メモリ:8GB以上
・記憶媒体:SSD推奨
高度な演算処理を行う動画編集ソフトでは、記憶媒体はHDDよりもSSDの方がおすすめです。ただSSDは高価で容量もHDDよりも少ないため、データ保存用に外付けHDDを用意すると心配ないでしょう。
動画制作にオススメの編集ソフトは?
有料の動画編集ソフトは、プロユースのため高いクオリティの動画制作が可能です。
お使いのPCがMacの場合は、無料ソフトのiMovieから有料のFinal Cut Pro Xへステップアップするのもいい選択でしょう。
動画制作の編集の際に、プロユースの動画編集ソフトは、クオリティの高い編集ができるのと同時に、パソコンにも高いスペックが求められます。
Adobe Premier Pro(Adobe社)
PowerDirector 365(CyberLink社)
DaVinci Resolve(Blackmagic社)
Filmora(Wondershare社)
Final Cut Pro X(Apple社)
iMovie(Apple社)
LIghtworks
Videopad
videoproc-vlogger
他多数
動画制作会社を選ぶポイント

企業や個人の方が、独自に動画制作する方法について紹介してきました。
自分でやりたいと思っていたけど、やっぱりちょっと不安。という方もいらっしゃいますよね?
というわけで、最後に(念のため?)プロの動画制作・映像制作会社に依頼する時のポイントをお伝えします。
プロの映像制作会社に依頼すると何が違う?
プロの映像制作会社は、テレビCMの撮影を多数行ってきた専門家集団です。「いい動画制作とは何か」、「見る人の心を動かす動画制作」を知り尽くしたプロフェッショナルと言えます。
宣伝やアピールを目的とした場合は、アクセス数といった「結果」を追求できるのも映像制作会社の強みです。
撮影だけでなく、企画・構成から公開までをパッケージ化したサービスも展開しています。動画制作の目的が明確なら、”丸投げ”も可能です。
映像制作会社の探し方
インターネットで検索すると、その映像制作会社にすればいいのか迷ってしまうでしょう。
その場合、求めている動画制作とマッチングするのかを判断するため、公開されている動画サンプルを視聴するのがおすすめです。
加えて、過去の実績や受賞歴なども確認すれば、品質にも安心できます。費用が不安な場合には、無料相談や見積りに対応しているかもチェックされて下さい。

動画制作の流れは?まとめ

動画制作の手順、初心者の方向けのノウハウ、プロの映像制作会社への依頼方法について、ご紹介しました。まとめると
①企画・構成
②撮影
③編集
④公開
(1)テーマを決めよう!何を伝えたい動画制作か?
(2)ターゲットは誰か?誰に動画を見て欲しいか?
(3)TV?YouTube?どこに動画を公開するか?
●基本的にカメラは固定
●音声にも配慮
●照明は必須
●カメラアングルと構図を覚えてワンランク上を目指そう
(1)撮影素材の読み込み
(2)不要な部分をカットする
(3)テロップを入れる
(4)BGM&効果音を入れる
(5)動画を書き出す
●動画編集に使うパソコンは?
●動画制作にオススメの編集ソフトは?
・CPU:intel Core i5、Core i7、Core i9
・メモリ:8GB以上
・記憶媒体:SSD推奨
Adobe Premier Pro(Adobe社)
PowerDirector 365(CyberLink社)
DaVinci Resolve(Blackmagic社)
Filmora(Wondershare社)
Final Cut Pro X(Apple社)
iMovie(Apple社)
LIghtworks
Videopad
videoproc-vlogger
他多数
でした。
動画制作の手順は、企画・構成、撮影、編集、公開になります。ターゲットとメッセージを絞り、完成イメージから逆算して作業すると動画制作はスムーズです。
しかし、独自に動画制作を行う場合は、技術だけでなく初期投資といった費用面でも不安が大きくなります。そのような場合には、プロの映像制作会社に依頼するのがおすすめです。
今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました!














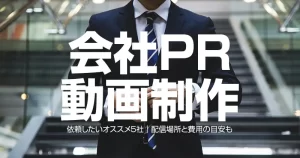

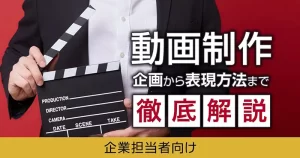
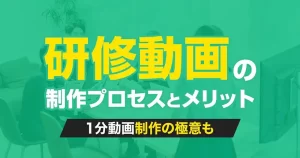

コメント