動画広告は一歩踏み間違えると失敗するリスクが高いことも事実です。
そこで今回は、マーケティングとしての目的を見失わずに動画広告を始めるコツを解説していきます。
動画マーケティングが失敗することも!?
視覚と聴覚の両方に訴えかけ、商品やサービスへの好感度を自然に高めてくれる動画広告。
「ぜひとも面白い動画を作り、成約率につなげていきたい」と思う企業も多いですが、動画制作に取り組む前に注意すべきポイントがあります。
企画段階でのぶれない姿勢
それは、「動画マーケティングの成功率は、企画段階でほぼ決まってしまう」ということ。
いくら動画としての価値があっても、本来の目的からかけ離れていては全く意味がなくなります。
だからこそ、企画段階で慎重な計画を練り、作成から投稿までぶれない姿勢を守る必要があるのです。
知名度を高めたり成約率につなげたりなど、動画マーケティングにはさまざまなメリットが期待できることから、完璧な成功にはならなくとも実行する価値があると思う方も多いでしょう。
企業にとっても失敗しないために
しかし、目的を見失った状態で動画マーケティングを試したばかりに、結果的に失敗するケースも少なくありません。
「ある程度の再生回数を記録できたもののコンバージョンに貢献しなかった」
「思った以上の再生回数を見込めなかった」
など、動画マーケティングの失敗例はいくらでもあります。やらないよりはやったほうがいいと考えることもできますが、製作時間や費用面でのコストをかけたうえでの失敗は、企業にとって打撃が大きいはず。
入念かつ慎重な企画が必要
同じ失敗を繰り返さないための対策が必要になります。
また、「動画が炎上した」「投稿先のSNSで批判的なコメントが相次いだ」など、明らかにマイナスな結果をもたらすこともあります。
だからこそ、手軽なマーケティング手法である動画広告は、入念かつ慎重な企画が不可欠になります。
成功する動画広告1:ブランディングを目的とする動画
これまで、動画マーケティングのリスクについてお話ししました。
簡単なようで意外に難しい動画マーケティングを成功させるには、動画制作の目的を意識することが大事です。
「何のために動画を作るのか」「誰に何をアピールするか」を明確にすることで、コンバージョン率が大きく変わるためです。
動画広告で取り入れたい目的の具体例としては、「ブランディング」「販売促進」「知名度」の3つがあります。
それぞれを詳しく見ていきましょう。
ブランドが持つ世界観は、ユーザーを魅了する
ブランディングを目的とする動画は、商品・価値のサービスを高め、ストーリーを持たせることが成功のコツです。
例えば高級な時計やブランド服、自動車などの広告には向いているでしょう。高級な商品を購入するユーザーの心理を考えると、その必要性がはっきりします。
ほかにも便利で安価な商品があるにもかかわらず、ブランド商品に興味を示すのは、そこに魅力的なストーリーがあるからです。
ブランドとしての世界観がユーザーを魅了し、「通常より高額でも購入したい」という意欲を起こさせるのです。
そのため、高額な商品を題材に動画マーケティングをするなら、ブランディングや世界観のアピールが効果的になります。
「商品を使うことで、ユーザーはどのような満足感を得られるのか」
「どのような気持ちになるか」
など、プラスの感情に訴えかけるアプローチが役立つでしょう。
価格競争に左右されなくなる
ブランディング目的の動画のメリットは、「価格競争に左右されないこと」でもあります。
購買率を高めたいあまりに安さを追求し、結果的に商品価値とイメージを落としてしまう企業も少なくありませんが、ブランディングを意識していればその必要性がなくなるためです。
ユーザーは安さを求めているのではなく、ブランドとしての魅力に惹かれているので、「買いたい」という気持ちがぶれることはありません。
成功する動画広告2:販売促進を目的とする動画
展開する商品やサービスがそれほど高額ではない場合、販売促進そのものにアプローチするのが効果的です。
いわゆるテレビコマーシャルの内容を取り込んでいけばわかりやすいでしょう。
商品・サービスの有能さや使い勝手をアピールし、ユーザーに伝えていくことがポイントです。
成約率につなげられる
販売促進を目的にした動画は、成約率に直結することが第一のメリットです。
ある程度のブランド力を持つ商品・サービスであればそれほど売り込まなくとも売り上げを拡大できますが、そうでなければ地道な努力が必要になります。
「どうしたら商品を買ってくれるか」
「どんなユーザーに需要がありそうか」
「どのようなトラブルを解決してくれるか」
など、実用的なメリットを盛り込んでいきましょう。
ブランディングが目的の動画は感情へのアピールが有効ですが、こちらでは具体的なアピールこそが成功の秘訣になります。
企業向けのアピールにも活用できる
このタイプの動画は一般ユーザーだけでなく、企業へのアピールとしても活用できます。
短い時間で詳しい説明が可能となるため、取引先も自然に商品・サービスへの興味を持ってくれます。
営業でプレゼンテーションをする場合には、ぜひおすすめです。
動画マーケティングは、成功率は企画段階で決まる・まとめ
最後に、再生数や知名度拡大に役立つ動画も、成功事例として数えることができます。
スタートアップから間もない場合や新商品をアピールする場合には、「いかに多くのユーザーに訴えかけるか」も重要なポイントになるためです。
ただ、ここで気をつけるべきポイントは、「同時に購買率も意識すること」です。再生回数だけにこだわると成約率につなげられないため、逆効果に終わるケースもあります。
動画としての面白さを残しつつ、結果を残せる動画を意識していきましょう。

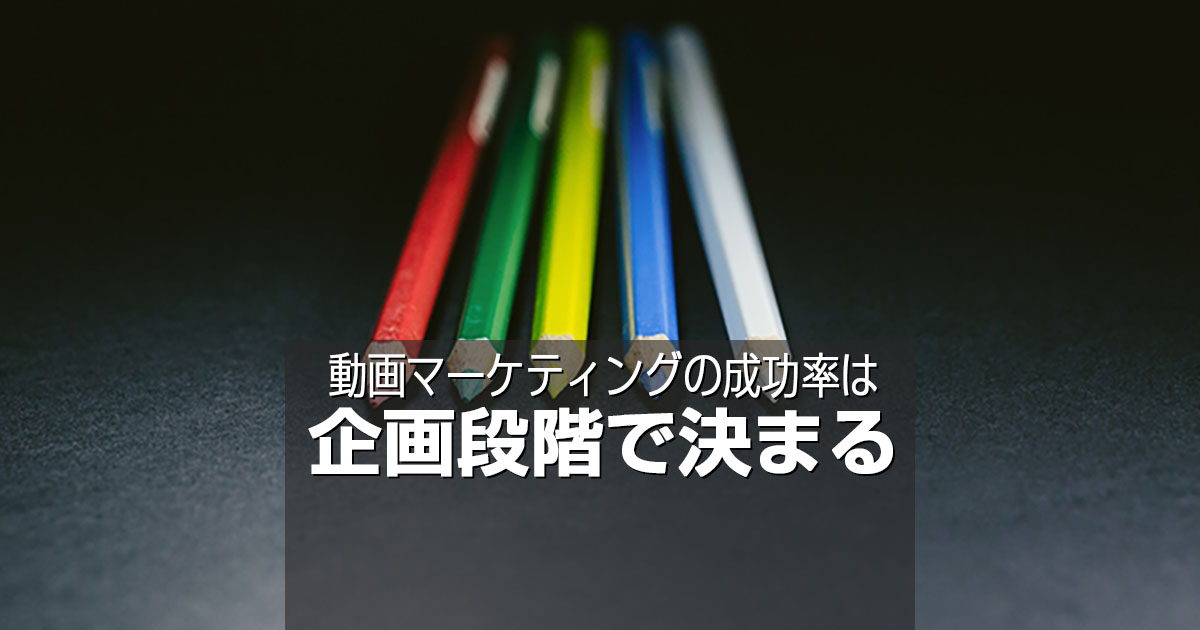
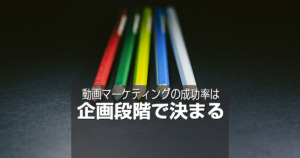






コメント