動画マーケティングを成功させるには、クリエイティブな戦略と同時に正確な分析が必要不可欠です。動画分析方法は、目的によって異なるため、それぞれに応じた対応が求められます。
今回の記事では、動画マーケティングに役立つ分析ポイントを挙げ、目的に合わせた分析方法をご紹介していきます。
動画広告のコンバージョンをさらに上げるために、ぜひ今回の記事をご活用ください!
動画広告の分析ポイント

動画の分析ポイントは、合わせて11つあります。
(1)「再生回数」:動画コンテンツに対する再生回数、クリック回数
(2)「ユニーク再生数」:何人の人が再生したかの回数
(3)「1回あたりの平均視聴時間」:総視聴時間における総再生回数
(4)「1人あたりの平均視聴時間」:総視聴時間におけるユニークユーザーの数
(5)「視聴率」:再生数におけるPV数
(6)「再生率」:再生時間における動画コンテンツの尺
(7)「再生完了率」:最後まで再生した数に対する全体的なアクセス数
(8)「瞬間視聴率」:瞬間視聴数に対する総視聴数
(9)「瞬間離脱率」:瞬間離脱数に対する総離脱率
(10)「誘導キーワード」:動画視聴を誘導したキーワード
(11)「動画のCV貢献数」:動画経由のCV数における、サイトのコンバージョン率
以上の11ポイントが、動画マーケティングの成功率を分析するための指標です。
Youtube、facebook、twitterなどにも、それぞれ名称は違うものの、かならず解析ツールが備わっています。
まずは、必ず定期的に確認しましょう。
最低でも押さえておきたいポイント4選
動画分析のポイントが11もあると、どれからはじめていいのかわからなくなります。
が、慣れないうちは、最低限の指標に注目すれば問題ありません。
最低でも4つのポイントについて分析をおこない、動画がユーザーにどのように受け入れられているのかを調べてきます。
その4つとは
再生回数
ユニーク再生数
1回あたりの平均視聴時間
1人あたりの平均視聴時間
です。
この4つのポイントから、もっとも弱いとされるポイントを見つけ出して、新たな分析を重ねて改善策を出していきましょう。
細かな分析を次回に活かすことで、動画マーケティングがより効果的になります。
動画広告の分析時の注意点
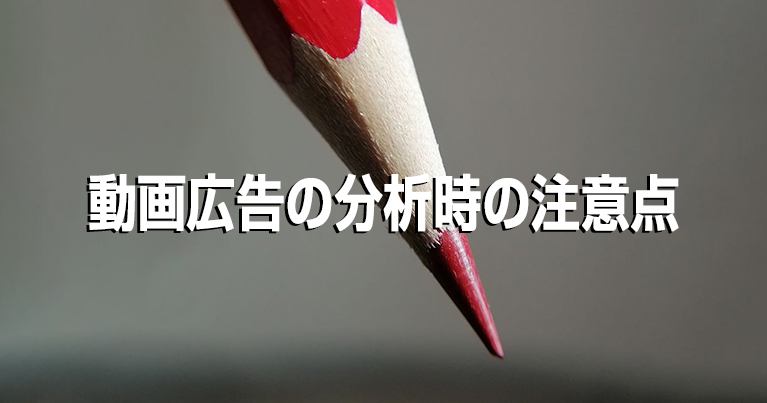
動画広告の分析時には、下記2点に注意しましょう。
再生回数にこだわるべきではない?
動画のアクセス解析を続けていくと、つい再生回数の増減に一喜一憂してしまいがちですが、それほど気にするべきではありません。
動画広告の最終的な目的はコンバージョン率の拡大、つまり売り上げアップであるためです。
例えアクセス回数が多くても、売り上げにつながらなくては意味がないとも言えます。そのため、再生回数だけでなくコンバージョン率も必ず確認し、結果に応じた改善策を探していきましょう。
(2)定期的にチェックすること
動画分析のコツは、やはり定期的かつ継続的な取り組みです。
日ごろから動画再生数やコンバージョン率を確認しておくと、動画の方向性や投稿タイミングなどを適切に把握できるようになります。
平日や休日など、ユーザーのスケジュールは日によって変わるため、日ごとに再生回数が増減するのはいたって自然なことです。
むしろもっとも多い日を探してタイミングをつかんでおけば、より効果の高い動画マーケティングを実践できます。定期的にアクセス解析をしていればおのずとわかってくることなので、ぜひ普段から分析する意識を持ちましょう。
具体的な3つの分析をする場合の指標

さて、ここからは動画分析における具体的なアドバイスを進めていきます。
「全体的な結果を分析する場合」「動画の質を分析する場合」「コンバージョン率を分析する場合」の3つの分析をする場合、適切な指標をご紹介します。
●全体的な結果を分析する場合
●動画の質を分析する場合
●コンバージョン率を分析する場合
全体的な結果を分析する場合
「再生回数」
「1人あたりの平均視聴時間」
「1回あたりの平均視聴時間」
「動画のCV貢献数」
が、この場合に確認すべきポイントです。
また、日々データを分析する際、日ごとの指標はもちろん全体的な動きもチェックしておきましょう。
アクセスが多い、少ない曜日と時間帯、また何を理由としてアクセスに変動があるかを確認します。そうすることで、次の改善策につなげていけます。
動画マーケティングにおける全体的な結果とは、再生回数とコンバージョン率です。
どれくらいの視聴率を獲得し、どれくらい売り上げに貢献したかが、最終的な指標となります。
動画の質を分析する場合
動画の質が良いか、ユーザーを飽きさせない工夫ができているかを見ていきます。この場合、
「再生回数」
「ユニーク再生数」
「1人あたりの平均視聴時間」
「1回あたりの平均視聴時間」
「再生完了率」
「視聴者離脱率」
を確認しましょう。
再生回数で全体的なアクセスを確認し、平均視聴時間、再生完了率、視聴者離脱率から、どのタイミングでユーザーが離れたのかを分析します。
ここで改善すべきポイントが見えてくるため、部分的な解決が可能になります。
ただし、ある程度の離脱は避けられないものだと考えましょう。増やさない努力を続ければ問題ありません。
コンバージョン率を分析する場合
爆発的な再生回数を期待できなくても、コンバージョン率が高ければ動画マーケティングとしては成功していると言えます。
その状態からアクセスアップにつなげると、より高いコンバージョン率を期待できるでしょう。
そのために分析を続ける必要があるのは
「動画のCV貢献数」
「誘導キーワード」
上記にプラスして
「再生回数」
「ユニーク再生数」
「1人あたりの平均視聴時間」
「1回あたりの平均視聴時間」
「再生完了率」
「視聴者離脱率」
を視野に入れた分析が必要です。
すでにコンバージョン率が高い場合には、動画の再生回数と動画の質に注目してみましょう。
それほどアクセスを見込めなくても売り上げ拡大ができているのは、商品・サービスに魅力があると考えられます。ストーリー性に富み、テンポの良い動画を提供すれば、売り上げをさらに上げることは決して難しい課題ではありません。
動画マーケティングにおいて、分析を重ねながら改善策を打ち出すことは必要不可欠なポイントです。
目的に合わせた指標を確認し、次回につなげていくといいでしょう。
増減に一喜一憂せず、長期的な視点が動画広告成功に役立ちます。
今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました!







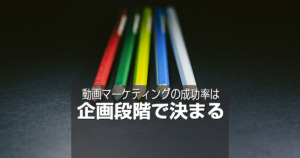

コメント