売り上げやコンバージョン率に、直接つながる可能性は低いものの、根強いファンを増やすのには大いに役立つのがブランディング広告です。
現在ではレスポンス広告だけでなくブランディング広告の動画・映像制作に着手する企業が増えていきました。
しかし、ブランディング動画を成功させる手法がいくつかあります。今回はその一つであるアニメーション動画についてお話しします。
アニメーション動画が効果的な理由
アニメーション動画とは、イラストなどをアフターエフェクツというソフトを使って、効果的に動かす動画のことです。
インフォグラフィック動画とも言います。(ここではアニメーション動画と表記します)
広告では実際の人間が出演する実写ものも多いですが、漫画家やイラストレーターが描いたイラストを用いた動画も数多く存在します。そのアニメーション動画広告がブランディングとして高い効果を生み出すことで、マーケティング担当者の興味を集めています。
ここでは、アニメーション動画だからこそのメリットを見ていくことにしましょう。
(1)情報量を調節できる
第一のメリットは、動画でアピールする情報量を適切な形に調節できることです。
動画広告は一般的に、数秒から長くても5分が適していると言われています。5分を超えるとユーザーにとっては重荷となり、離脱率が高まってしまうためです。しかし、短ければ短いほどいいわけではなく、企業が伝えたいメッセージをユーザーにしっかりとアピールしなければいけません。
そこで、アニメーション動画が役立ちます。
実写版の動画よりもイメージが強烈でないため、ユーザーに過度なプレッシャーを与えずに動画に引き込むことができます。情報量が多い動画を配信する際には、ぜひ試してみるといいでしょう。たとえば『90%アップ』とか『7800万円の増益』など、細かい数字を強調したい場合があるとします。
これをナレーションでおこなうと、ほとんど記憶には残りません。そして見ている人が飽きてしまう原因を作ります。そんな時にアニメーションを使うと、とても効果的です。視聴者に飽きられることなく、記憶にも残せるというメリットもあります。
(2)ストーリーにスムーズな導入ができる
また、場合によってはアニメーション動画のほうが実写動画よりも効果的な場合も少なくありません。
CMではモデルや俳優・女優、アイドルなど、きらびやかな世界で活躍する芸能人が出演しています。高級品や高度なサービスなど、ハイステータスを主張するブランディングには最適ではありますが、どちらかというと庶民的な商品・サービスのアピールには向きません。ここでアニメーション動画を使うことは、ユーザーに親近感を抱かせることにも役立ちます。
実際に、アニメーション動画のほうが親しみやすいことから、ユーザーが動画を「自分事」としてとらえやすいというメリットもあります。ブランディング広告と同様にダイレクトレスポンス広告にも効果的。両方を狙いたい場合にはぜひおすすめです。
(3)表現が自由
実写版よりもアニメーション動画のほうが表面上の制約が少ないというメリットもあります。
実写版で何らかの不具合が生じると、多くのケースで撮り直しを要求されるため、時間・費用のコストが大きくかかってしまうもの。一方、アニメーション動画では該当箇所を修正するだけで済み、比較的柔軟な対応ができます。
加えてシリアスな内容でもユーザーに負担を与えすぎないことも、アニメーション動画ならではのメリットです。介護やいじめなどの動画はどうしても内容が重くなりがちですが、アニメーション動画なら必要なメッセージを伝えつつ、ユーザーに難なく受け入れてもらうことができるでしょう。
アニメーション動画を成功させるための3つのコツ
さて、ここまでアニメーション動画のメリットをお伝えしました。次はアニメーション動画を成功させるための、実用的なコツについて解説していきます。
(1)スタイルを決める
最初に、アニメーションのスタイルを決めます。イラストのタッチには実にいろいろな種類があります。
男性向けであったり女性向けであったり、華麗であったりシンプルであったりなど、スタイルによってユーザーに与える印象は異なります。
数あるスタイルのうちから、どれが企業の方針やストーリーに向いているのかを選んでいくのがベストです。数パターンを作って差支えない限りで第三者に聞いたり、社内で検討したりしても良いものを決定できるでしょう。
(2)ペルソナを作る
アニメーション動画のスタイルが決まったら、ペルソナを作りましょう。
ペルソナとは、商品・サービスに興味を持つであろうユーザーです。主人公に設定することで、より親近感が生まれます。
ペルソナの年齢、性別、好み、職業など、思いつく限りの属性をペルソナに盛り込んでいきましょう。自分自身にそっくりなペルソナを見出すことで、ユーザーは商品・サービスへの理解度を深めていきます。
(3)色を活用する
アニメーション動画を成功させるためには、適切な色を選ぶことも大事です。
スタイルやペルソナに比べて重要度が低いように思われますが、実は色こそがユーザーに商品・サービスのイメージを強くアピールする要因なのです。例えば強烈な個性を出すなら赤、かわいらしさをアピールするならピンク、クリーンなイメージを強調するなら白か緑など、選べる色は多岐にわたります。
カラーバリエーションは何を選んだらいいのかわからない点もありますが、色彩感覚を学べばある程度はご自分でも適したものを選べるようになります。心配であれば何パターンか作って第三者に判断してもらうか、社内で意見を交わしたうえで決定するといいでしょう。
ブランディングにも効果的なアニメーション動画。成功のコツ・まとめ
商品・サービスのストーリーを伝え、企業に対しての認知度と理解度を高めてくれるブランディング広告。
これまでは売り上げ促進とコンバージョン率のアップを主な目的とするダイレクトレスポンス広告が主流だった企業からもブランディング広告が注目されるようになりました。
通常の実写動画が重く感じられた場合、アニメーション映画でライトに演出するという手段も有効です。適切なスタイルとペルソナ、色を選んでいけば、確実にユーザーへのアピール力が強まるでしょう。
実際に配信されているアニメーション動画をチェックしつつ、それぞれのコツやスタイルを見出していくのもおすすめです。動画広告には数々のエッセンスが込められているため、視聴しながら内部を観察していくことで、成功ポイントを発見できます。
今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました!



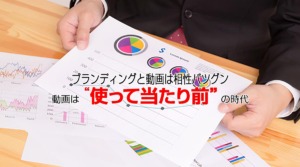

とは?メリットと種類|成功するポイントも紹介-300x158.webp)


コメント